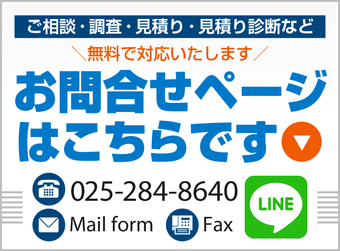火災が発生した際に自動で消防署に通報をしてくれる火災通報装置。
火災の発見から通報までを自動で行うことで、消防隊の到着が早まり、被害を最小限に抑えることが出来ます。
また、通報の手間を省くことで、1分1秒を争う避難活動で、十分な人員を割いて、活動に当たる必要があります。
この記事では、火災通報装置の自動通報化の工事について解説していきます。
こんなことでお困りではありませんか?
✅消防署から消防設備点検するよう言われた。
✅今の業者さんは呼んでもすぐに来てくれない。
✅消防設備工事料金が高い気がする。
✅消防点検の元請け会社と直接契約したい。
✅消防設備だけでなく電気設備の面倒も見て欲しい。
などでお困りの方は下記より電話・メールにてご連絡をお願い致します。
※強引な営業・販売は致しませんので、お気軽にご連絡ください。

自動通報の義務化
平成25年12月27日に公布された消防法施行規則の一部改正により6項口にあたる防火対象物(養護老人ホームや障害児入所施設など)では、火災通報装置と自動火災報知設備の連動が義務付けられました。
この法律は、認知症を持つ高齢者施設で多数の死傷者を発生した火災事例を教訓とし、火災発生時の消防機関への通報を自動化し、死傷者の発生を予防するために改正されました。
工事開始

老人福祉施設のお客様よりご依頼いただきました。
法改正で義務化されてから、こちらの施設はまだ工事が済んでおりませんでした。
弊社で点検などはしておらず、新規でのご依頼となります。

こちらが火災受信機から送信される火災の信号が火災通報装置に送信されないようにする「連動停止スイッチ」になります。
今回の工事はこの装置を火災通報装置と火災受信機の間に設けることが目的となります。
各機器間の配線工事を行い、連動停止スイッチに接続します。
受信機と火災通報装置が隣同士だったので、ケーブルを通す作業はさほど時間はかかりませんでした。
工事後

工事完了後の通報試験は良好でした。
自動火災報知設備と連動させる場合は、受信機と発信機に黄色の注意書の貼付が必要となります。
万が一の火災が発生した場合は、火災の感知と同時に消防署へ通報されるため、非常に有効な仕組みとなります。
しかしながら、非火災報(感知器等の誤作動)の場合も同じように通報されてしまうため、その場合の対処をどうするかという点は、事前に決めておく必要があるかと存じます。
非火災報で大事なことは、消防署からの呼び返し電話に応答し、火災では無いことを伝えることです。
もしも、まだ工事を終えられていない施設がありましたら、お気軽にご連絡ください。
✅消防署から消防設備点検するよう言われた。
✅今の業者さんは呼んでもすぐに来てくれない。
✅消防設備工事料金が高い気がする。
✅消防点検の元請け会社と直接契約したい。
✅消防設備だけでなく電気設備の面倒も見て欲しい。
などでお困りの方は下記より電話・メールにてご連絡をお願い致します。
※強引な営業・販売は致しませんので、お気軽にご連絡ください。